音楽家としてこれ以上ないほどのハンデを抱えながら、数々の名曲を生み出したルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。
その事実を初めて知ったとき、誰もが不思議に思うのではないでしょうか。
音楽家にとって“聴く力”は命。
にもかかわらず、彼は晩年には完全に耳が聞こえなくなっていたといわれています。
それなのに、あの「第九」や後期ピアノソナタのような深遠で豊かな音楽をどうやって作り上げたのか?
この記事では、ベートーヴェンが「音のない世界」でどのように創作を続けたのか、その秘密をわかりやすくご紹介していきます。
この記事を書いている人

アガサ
このブログの運営者及び管理人
3歳からピアノを始め、クラシック音楽歴は30年以上。結婚・出産を経て育児の合間にピアノを再開し、念願のグランドピアノも迎えました。
現在はピアノ教室向けのグラフィックデザイナーとして、全国の先生方をサポートしています。
ピアノとクラシックをこよなく愛する主婦が、音楽やピアノにまつわる情報を気ままに発信中です♪
- ベートーヴェンの生涯や作曲の背景に興味があるクラシック音楽ファン
- 音楽家の苦難や努力、創作の秘密を知りたい方
- 「耳が聞こえなくても創作できるの?」という疑問を解消したい方
- 音楽の歴史や作曲技法の奥深さを学びたい初心者から上級者までのピアノ愛好者
本当に耳が聞こえなかったの?

「耳が聞こえないのに作曲?」という話はあまりに衝撃的ですが、実際のところベートーヴェンはどの程度、いつから聴力を失っていったのでしょうか?
ここではその経緯を見てみましょう。
少しずつ、でも確実に進行していった難聴
ベートーヴェンが耳に異変を感じはじめたのは、20代後半(おそらく1790年代末頃)だとされています。
最初は「耳鳴り」や「人の声が聞き取りにくい」といった症状でしたが、30代半ばには演奏家としての活動が難しくなるほど、聴力は悪化していきました。
彼はこの頃から、人前での演奏や社交の場を避けるようになります。
あの情熱的な音楽からは想像しにくいですが、実は孤独や絶望に悩んでいた時期でもあるんです。
晩年には、ほぼ完全に聞こえていなかった
40代以降、ベートーヴェンの聴力はほとんど失われていたとされています。
日常会話もままならず、他人とのやり取りは「会話帳(カフェや家で人に筆談してもらうノート)」に頼っていました。
つまり彼の後期作品――《第九》や《ミサ・ソレムニス》などの大作は、“ほぼ完全に聞こえない状態”で書かれたことになります。
それでも創作をあきらめなかった
耳が聞こえなくなるというのは、音楽家にとって致命的ともいえる出来事。
しかしベートーヴェンは作曲をやめるどころか、むしろその後に最も革新的で壮大な作品を生み出しています。
「音が聴こえなくても、心の中には音楽が鳴り続けていた」
そんなふうに表現されることもある彼の創作は、果てしなく偉大な傑作であることは間違いありませんよね。
難聴の原因は何だったの?

ベートーヴェンの難聴の原因については、実はいまだにはっきりとわかっていません。
ただし、いくつかの有力な説があり、医学的な検証や遺品の分析からもいくつかの手がかりが見つかっています。
鉛中毒の可能性
2000年代に行われた彼の遺髪と頭蓋骨の分析により、「体内に通常よりはるかに高い濃度の鉛が蓄積されていた」という結果が出ています。
このことから、慢性的な鉛中毒が難聴の一因になった可能性があると考えられています。
鉛は当時の酒や薬、食器などに含まれていたため、知らないうちに日常生活の中で摂取していたかもしれません。
耳の病気や神経性の要因も
それ以外にも、耳の感染症(中耳炎など)や内耳神経の障害といった、より直接的な耳の病気によるものだった可能性もあります。
またベートーヴェン自身は、医学的な記録の中で「消化器の不調」や「腹部の痛み」なども訴えており、体質的・神経的な不調が複雑に絡んでいた可能性も否定できません。
原因はひとつではないかもしれない
現在では、「鉛中毒・病気・体質」など複数の要因が重なった結果として、徐々に聴力を失っていったと考える専門家が多いようです。
どれか一つに絞ることは難しいですが、彼の創作を阻むには十分すぎるほどのハンデだったことは間違いありません。
どうやって作曲?耳が聞こえない中での工夫
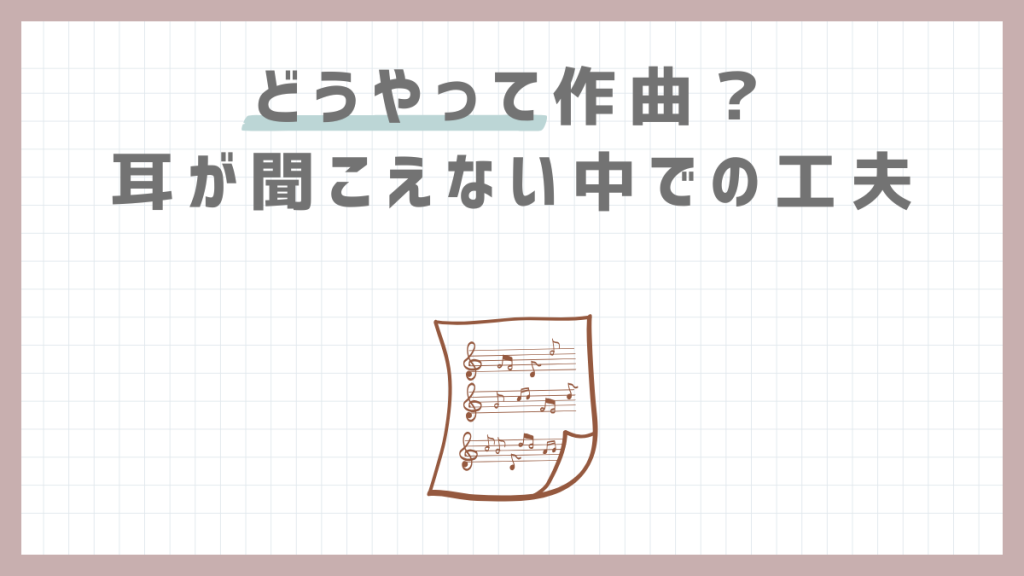
「耳が聞こえないのに、どうやって曲を作ったの?」多くの人が気になるこの疑問。
ベートーヴェンは、ただ奇跡のような才能で書いていたわけではありません。
彼なりの工夫や“音楽の感じ方”があったのです。
頭の中で音を「聴いていた」
ベートーヴェンは若い頃から、楽譜を見ただけで音が頭の中に“聞こえるほどの読譜力と音感を持っていました。
いわゆる「内なる耳(内的聴覚)」が非常に発達していたんですね。
耳が聞こえなくなってからも、その能力をフル活用して作曲していたと考えられています。
彼の中には、まるでオーケストラが鳴っているかのように、音楽が“思い浮かんでいた”のでしょう。
鍵盤の振動を「体で感じて」いた
実は、まったくの無音ではなかったという説もあります。
耳ではなく、“体で音を感じていた”という記録が残っているのです。
たとえば…
- ピアノの響板に棒をくわえて、歯から振動を感じる
- 床に耳をつけて、低音の響きを確かめる
といった驚きの方法で、自作の音楽を“確認”していたとされています。
まさに、音を「聞く」のではなく「感じる」作曲法。音楽に対する情熱が伝わってきますね。
楽譜とにらめっこで、徹底的に練り上げた
ベートーヴェンは、スケッチ帳(アイデア帳)に大量のメモを書き、何度も何度も推敲を重ねて作曲していました。
同じフレーズを何十回も書き直したり、構成を少しずつ練り直したり、「天才が一気に書き上げた」どころか、ものすごく努力型の作曲家だったのです。
耳が聞こえなくても、「楽譜を通して音楽を視覚的にイメージする力」と、「とことん突き詰める粘り強さ」があったからこそ、あれほどの作品が生まれたのでしょう。
ベートーヴェンの難聴が音楽に与えた影響
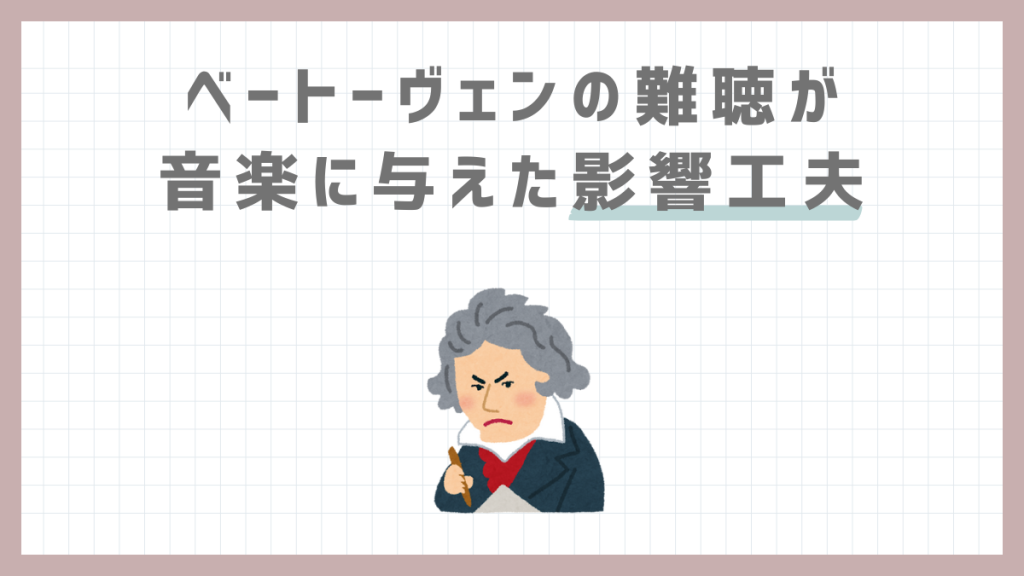
耳が聞こえなくなっても作曲をやめなかったベートーヴェン。
その後の作品には、難聴というハンディキャップが逆に“力強さ”や“革新性”として表れたとも言われています。
より内面を掘り下げた音楽へ
聴覚を失っていく中で、外からの刺激よりも自分の内側にある音楽を追求するようになった、とも考えられています。
それが、作品により深い感情や哲学的なニュアンスをもたらしたとも。
例えば、後期のピアノソナタや弦楽四重奏には「静けさ」や「孤独感」、あるいは「祈り」にも似た深い世界が感じられます。
聞こえないからこそ、“音のない時間”や“沈黙”の美しさにも目を向けられたのかもしれません。
革新的なスタイルが生まれた
耳が聞こえなくなったことで、常識や過去のスタイルにとらわれず、自由に作曲できるようになった面もあります。
たとえば…
- 交響曲第9番では、それまでになかった声楽入りの交響曲という新しい形を生み出した
- 形式や調性にこだわらず、より自由で個性的な構成を採用した作品も増えた
周囲の評価や音のバランスに頼れないぶん、「自分が信じる音楽」を突き詰めた結果、より大胆な表現へと進んだのです。
“限界”が、“独創性”につながった
難聴というのは、音楽家にとってこれ以上ないほどの試練だったはずです。
けれどベートーヴェンは、それをただの“障害”で終わらせず、自分の音楽をさらに進化させる原動力にしました。
「聞こえないけど、創りたい」
その気持ちの強さが、後世まで語り継がれる名曲たちを生み出したのです。
まとめ

ベートーヴェンは、耳が聞こえなくなるという音楽家にとって最大の試練を経験しました。
しかし、そのハンデをただの障害にせず、自分の音楽を深め、革新へと昇華させたことは本当に驚きです。
聴力を失っても頭の中で音を“聴き”、体で振動を感じ、楽譜と向き合いながら何度も推敲を重ねていった彼の努力と工夫があったからこそ、今なお愛される名曲が生まれたのだと感じます。
難聴の原因には諸説ありますが、それを乗り越えた強い意志と才能が、彼をただの天才ではなく、不屈の作曲家にしました。
この事実は、どんな状況でも諦めずに自分の道を追求することの大切さを教えてくれますね。
最後まで、ご覧いただきありがとうございました^^










